読書をして1冊読み切った瞬間は、とても勉強になった気がして、満足してしまいませんか?
しかしながら、どんなことが身についてきたか、あるいはその本の説明ができるかと言われると…
私は説明できるものがない読書を繰り返していたと振り返っています。
読書を結果に繋げたい。記憶に留めたい。成果を日常生活で発揮したい。
このような思いを持って、樺沢紫苑さんの「読書脳(サンマーク出版)」を手に取りました。
著者の樺沢紫苑さんを知ったのは、You Tubeの動画がきっかけでした。
とある事情でメンタル不調にかかる知識が必要となり、
色々調べる中で、樺沢さんの動画に出会いました。
樺沢さんは精神科医で、朝散歩を勧めておられ、そこから著書にも興味を持ちました。
私が特に大切だと感じたところについて、書きたいと思います。
学んだことをアウトプットする
その本の中で、重要だと思ったことを、次の方法で1週間に3〜4回アウトプットすることで、
記憶に定着させる方法です。
- 人に話す。
- Xで呟いてシェアする。
- ブログなどで書評や感想を書く。
ここでは、私なりの解釈で書いていますので、実際には本を読んでいただきたいと思っています。
今回の記事も、この書籍を読んで、アウトプットを実践しているものです。
こうやって記事にするにも、自分がどこを理解できていて、それを言葉に表せているか、
を振り返る事ができ、アウトプットの大切さを実感しています。
スキマ時間を活用する
著者の樺沢さんは月に30冊をスキマ時間だけで読まれるとのこと。とても多いと思います。
こちらも私の解釈となりますが、
- 通勤電車の中
- 昼休みの食事の後
- 自宅での休憩時間中
などの際に、「何となくスマホを触っている」のであれば、それを読書の時間にする!
というものです。
私の場合ですが、職場の昼休みは1時間、そのうち30分は食事、
その後15分はコーヒーを飲んだり歯磨きをしたりして、残りの15分を読書の時間にあてています。
これ以外に、何かの合間、合間にスキマを見つけたら、少しでも読書、を意識しています。
これを意識することで、少しずつですが読書の習慣が身につき、
着実に読める冊数も増えてきました。
スキマ時間の活用は、本を読む時間がないという意識から、
読書の時間を作り出す=そこから読書の効率を上げる、への意識改革だと考えました。
速読ではなく深読
樺沢さんの本を読むことの定義は、大きくは次の2点とのことです。
- 内容を説明できること。
- 内容について議論できること。
見出しの「深読」という言葉は樺沢さんが考えられたもので、「議論できる水準」にまで内容を理解する読み方を表現されています。
また、速読を否定されているわけではなく、深読ができた上での速読や多読を目指せばいい、
と述べておられます。まさに、鬼に金棒のような読書法だと、個人的には思っています。
まとめ
樺沢紫苑さんの「読書脳」について、私がポイントだと感じ、
今まさに実践しているところは次の3点です。
- 学んだことをアウトプットする=記憶に定着させる
- スキマ時間を活用する=読書の時間を作り出し、読書の効率を上げる
- 速読ではなく深読=議論できる水準で読む
読書については、100人いれば100通りの読み方があると思います。
その人が読みたいように読めばいい、それも正解だと思います。
私の場合は、読書した時間を結果や成果として日常生活で発揮したい、という思いがあります。
樺沢紫苑さんの「読書脳」はそんな思いを形にできる1冊になるかもしれません。
それでは、本日もありがとうございました!
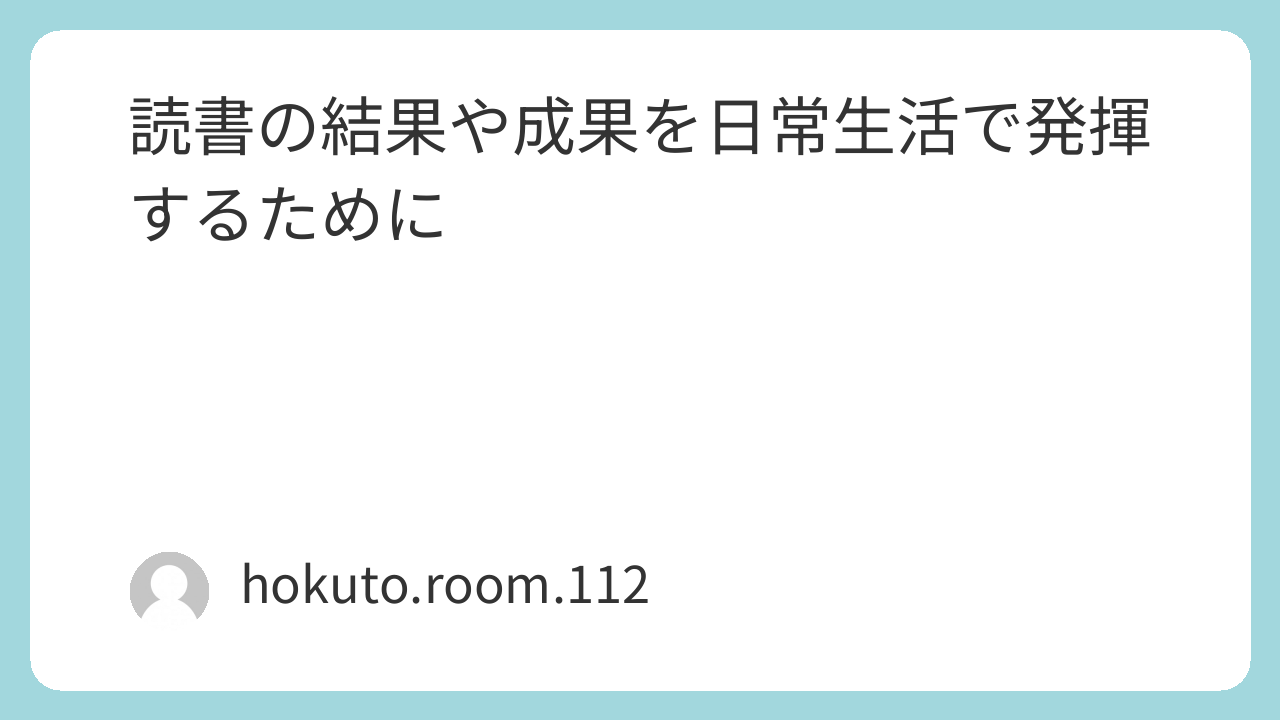
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d4e70f3.c7f8d651.4d4e70f4.bdb699cd/?me_id=1213310&item_id=21006617&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0722%2F9784763140722_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

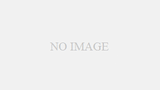
コメント